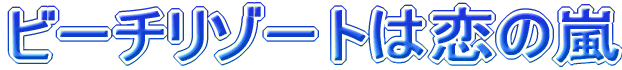
2005/12/20 更新
(1)
「ビンセント、遅いなあ」
待ち合わせの時間から、もう30分も過ぎている。出発時刻までもうそんなに余裕もないというのに、広いロビーをキョロキョロと見渡してみても、彼の姿はまだ見えない。不安を覚えながら、先程から何度も確認している腕時計に恨めしげな視線を送って、秋生は溜息をついた。
ジーンズに白いTシャツ。その上にジャケットを羽織った秋生の足元には自分のと、会社から直接駆けつけてくる予定のビンセントのスーツケースの、二つがあった。五泊六日の旅行の予定である。
少し大きめな荷物は、帰りのお土産を考えての事である。行き先は南の島のビーチ・リゾートだが、一応、パーティー用のスーツや靴も入っていたりする。ビンセントの会社と取引のある世界的に有名なホテルグループが、南の島を一つ買い上げて作った豪華なリゾートホテルらしく、世界中の金と暇を持て余した裕福な人達を対象にした、予約するのも難しいという凄いところなのだ。
「招待されたのですが、行ってみますか?」
それは一ヶ月前の事。ビンセントが会社から帰ってくるなり見せてくれたパンフに、秋生は目を丸くして感嘆の声をあげた。
小さな南の島の原生林をそのまま残して、豪華ホテルとコテージが作られ、そこでゆっくりとくつろぎながら、ビーチではいろいろなマリンスポーツが楽しめるようになっているらしい。
そんな贅沢を尽くしたビーチ・リゾートに招待なんて、東海公司という香港でも五本の指に入る大企業の社長であるビンセント・青だからこそ来る話で、平凡な小市民である自分には、絶対に縁のない話である。金持ちで有名人な恋人を持つ身の上としては、そのありがたい招待の恩恵を断る理由など何処にもなかった。
「行く行く!!行きたい!!」
瞳をキラキラと輝かせて叫ぶ秋生の様子を見て、苦笑しながらも、愛すべき恋人の願いをビンセントは快く聞き入れた。そもそもその笑顔を期待していた彼は、実はもうとっくに予約を入れてあったりするのだが、秋生には内緒である。
「それでは来月の連休に行きましょう」
「本当!!ワーイ!!」
秋生は嬉しさの余りにビンセントに抱きついてしまう。そんな無邪気な恋人の身体を抱き締めながら、ビンセントは頭の中で、スケジュール調整に大変であろう有能な秘書の廖の困った顔を思い浮かべた。
「そのために暫く仕事が忙しくて、すれ違いになるかもしれませんが、我慢していただけますか?」
ラブラブな恋人同士の唯一の悩みが、ビンセントの仕事が忙しくて、なかなか一緒にいられないという事だとは、他人が聞いたら呆れてしまう贅沢な悩みかもしれないが、本人達には大問題であった。
「寂しいけれど我慢する。あっちにいけばゆっくり過ごせるんでしょう?」
「ええ、二人でゆっくりと楽しみましょうね」
南の島のリゾートで過ごす二人きりの濃密な時間に期待に胸を躍らせて、うっとりと酔いしれた秋生は、そのままビンセントの甘い口づけを受けて、身も心も彼の腕の中に委ねたのであった。
(それなのに、なんだよ)
ビーチ・リゾートどころか待ち合わせに遅刻だなんて絶対に許せない。
この一ヶ月、五泊六日の休暇を捻出するために、いつにもまして忙しかったビンセント。すれ違いの日々が多かったのに我慢して堪えた身の上としては、旅行が駄目になるなんて事を考えたくはなかった。実際、ビンセントがこの旅行のために随分無理をして頑張ってくれていたのを秋生はよく分かってはいたが、当日に遅刻だなんて問題外である。
ブルブルブルッ
その時、上着のポケットに入れていた携帯が着信を告げて振動を始め、秋生は慌てて取り出した。相手は待ち人のビンセントである。電話してくるなんて嫌な予感が一瞬、秋生の心に過ぎって、携帯に出ることを躊躇わせたが、辛抱強くコールが続くので、仕方なく覚悟を決めて携帯に出るのであった。
「もしもし、ビンセント、どうしたの。搭乗までもうそんなに時間がないよ」
動揺を隠せずに声がついついきつくなってしまう。
『秋生、どうしてもやっておかなければならない急な仕事が入ってしまいました。チケットはお持ちでしたよね。すみませんが先に行って下さいますか。.後からすぐに追いかけますから――』
「えっ、先に行くの。僕一人で・・・・・・」
すぐにと言われても、本当にすぐ来るのだろうかと不安にならずにはいられない。
『ええ、向こうの飛行場には迎えが来ますので何も心配はいりません。私からちゃんと連絡しておきますから』
このままビンセントが間に合わず、旅行が駄目になってしまうよりは、先に行って待っているほうがマシかもしれない。何より彼の言葉を信じて待つことが出来ないようでは、恋人失格である。
「うん、わかったよ。すぐに来てよね。待ってるから。きっとだよ」
『はい、本当にすみません。私も貴方と過ごせる旅行を本当に楽しみにしていますから、用事が片付き次第すぐに参ります』
「僕だって凄く楽しみにしてるんだから。早く来てね」
普段、面と向かっては言えない事も、電話だと実に素直に伝える事が出来る。
『はい。愛していますよ、秋生』
「僕もだよ、ビンセン」
不安でいっぱいだった心は、愛する彼の電話でスッキリ解消してしまい、それどころか秋生の心には、二人きりで過ごすビーチ・リゾートへの夢がもう少して本物なるのだという期待に大きく膨れ上がって、ワクワクしてくるのを抑えられなくなってしまうほどである。
(迎えが来てくれるなら何も心配はいらないよね。ビンセントが来るのを待っていればいいもんね)
根が単純というか素直な秋生は、先程までの不安は何処吹く風やら、笑顔を取り戻すと、上機嫌で二つのスーツケースをヨイショッと持つと、出発ロビーへ向かって歩き出すのであった。
香港からマレーシアの首都クアラルンプールへ、マレーシア航空で一時間半余りの旅の後、到着ゲートから出てきた秋生を待っていたのは、ウエルカムと書かれた名前入りのプレートを持ったスチュワーデスの綺麗なお姉さんであった。
でも、見たことのない制服で、なんでかなあと思いつつも、彼女の笑顔に惹きつけられ、丁重に案内されたのは、なんとプライベート・ジェットだった。
機体には目的地のビーチ・リゾートを経営するホテルグループの名前があり、なんと、秋生のためにわざわざ迎えに来てくれたらしい。
話を良く聞いてみると、島には専用の飛行場があって、世界中からプライベート・ジェットで飛んでくるお客さんも多いという。また、大型クルーザーで来る人のために、港も完備されているらしい。もう、それを聞いただけで、秋生はすっかり舞い上がってしまった。
ビンセントも確かにお金持ちで、一体どのくらいの資産を持っているのか確かめた事はないが、時々、高価なものをプレゼントされて驚かされる事はあっても、普段は割と普通な生活を送っていると思う。
プライベート・ジェットとかクルーザーで世界中を移動するなんて、遠い世界の極少数の人ぐらいに思っていたのだが、そんなにいるのだろうかと疑わずにはいられない、余りにもかけ離れた世界に、庶民な自分を思い知らされてしまった秋生は、こんなところに自分がいていいのだろうかと思ってしまった。
ジェットの窓から見える南の青い海に点在する島々。やがて離陸体勢に入ったジェットは、その島の一つへと静かに着陸した。
タラップを降りると、空調のきいた機内とは全く別のムッとする熱気を帯びた空気に包まれたが、すぐに迎えのリムジンに乗せられて、宿泊予定のコテージへと案内された。
「えっ、嘘〜っ、本当に此処?」
コテージと聞いていたので、庶民な秋生が想像していたのは、日本の海の家をちょっと豪華にした程度のものであったが、目の前にあるコテージは、ちょっとした豪邸であった。
周囲にはいくつかのコテージが建っていたが、一つ一つがプライベートを尊重に出来るように、充分に広い庭の樹木によって隔てられていた。おまけに案内されて入った部屋は、二人で過ごすには余りにも広く、家具や調度品まで全てが贅沢な物ばかり。裏庭には専用のプールがあり、おまけにその先にはプライベート・ビーチが広がっていた。
「ヒャーッ、ちょっと凄すぎ!!」
聞くところによると、どうもコテージの中でも一番豪華で、VIP専用らしい。案内してくれたコテージ専用の執事のマールさんが、電話で呼べば昼夜関係なく食事やお世話をしてくれるということであった。
「お世話になります」
「いえ、とんでもございません、工藤様。どうぞごゆっくりお楽しみ下さいませ」
ついついペコリと挨拶をしてしまう秋生に、大事なお客様で、社長直々に丁重なおもてなしをするように伺っていますからと、反対にマールに恐縮されてしまった。
(ビンセントって一体!?)
凄い人だとは知っているものの、こんなところに招待されるなんて自分が思っていた以上に凄いんだと、認識を新たにした秋生は、少し位の遅刻はおおめに見てあげようと、凄く豊かな気持ちになるのであった。
その後、すぐにプールで水遊びした秋生は、執事のマールさんが用意してくれた釣り道具を持って、プライベート・ビーチでのんびりと釣りを楽しんだ。
船がつけられるようになっている桟橋の下には、色とりどりの熱帯魚達が群れて、面白いように釣れるのだ。熱くなれば海に飛び込んで少し泳いで、また、釣りに興じたりして、秋生は夕方まで、時間を忘れて楽しんだ。
夜は、コテージのテラスに豪華なディナーが用意され、松明の明かりに照らされ、夜空いっぱいの星を眺めながら、食事を楽しんだ。
そこへビンセントから電話が入り、秋生は電話で胸いっぱいの喜びと感謝を告げた。
『どうです、気に入っていただけましたか?』
「うん。凄く素敵なところだよ。ありがとう。海が凄く綺麗で魚がいっぱいいるんだ。今日は釣りをしたんだよ」
『それは良かったです。明日の午後にはそちらに迎えると思いますので、もう少し待っていてください』
「うん。本当に素敵なところだよ」
ついつい秋生の口調は甘えた感じになってしまう。確かに素晴らしい自然と至れり尽せりのサービスに満足して、楽しんではいるけれど、二人ならばもっと楽しいはずなのにと、思ってしまったからである。
豊かな自然の中に溶け込んでのんびりと過ごしていると、都会の喧騒の中で生活している時と違って、とても穏やかな気持ちになれるが、広い世界の中でたった一人きりでいる自分というものも感じさせられ、自分の側にいるべき存在をつい思い出してしまうのである。
(早く来てね。寂しいよ)
そう素直に口に出来たらもっといいのだが、たった一日も一人でいられないなんて、いい歳して少し恥ずかしいような気がして、それはさすがに言えずに、元気で楽しんでいると強がりを言って、秋生は電話を切ってしまった。
少し後悔したが、明日には会えるのだからと思い直せば、それぐらいは我慢できると思った。
「どうして、来ないんだろう」
二日目、午前中はゆっくり眠ってからプールで遊んで、午後には向かうと言ったから、夕方には来るかと思って、釣りからもそうそうに帰って、シャワーを浴びて、今か今かと待ち続け、おなかが空腹を訴えても、ビンセントが来てから一緒に食べようと思って、ひたすら我慢しているのに、いつまでたってもビンセントは現れない。
「何かあったのかな?」
と心配になって電話してみても、会社の方はすでに退社していると告げられ、携帯は全然繋がらない。
今、きっと来ているに違いないと夜空を眺めて、飛行機の光が見えないかと思って暫く眺めてみたが、美しい夜空も次第に空しく思えてきてしまい、なんだか食欲もなくなって、やりきりない寂しさと不安を抱えたまま、ふて寝してしまった。
三日目の朝、目が覚めて意識がはっきりするなり、もしかしたらビンセントが来ているかもしれないと、寝室を飛び出して探してみたが、結局、姿を何処にも発見する事が出来なかった。
さすがに昼は何か食べようと、マールさんにサンドイッチを頼んでみたが、いざ食べようとすると、全然喉をとおらなかった。
(もう三日もほったらかして、どういうつもりだろう)
いつもはもっと会えない事もあるけれど、近くに知り合いがいるし、それなりに自分の学生としての日常もあるから、寂しいと思いながらもなんとか我慢することが出来るが、折角の楽しいはずの旅行で一人でいるなんて、空しさも倍増するような気がする。
いくら忙しいからといって、本当に大事な恋人を何日もこんなところへ放っておくなんて、愛が足りな過ぎると思う。
(僕ってもう愛されてないのかな)
何か事情があるのだったらせめて連絡ぐらいくれればいいのに、それすらないなんておかしい。
「工藤様、よろしかったらホテルの方にもいろいろと設備がございますから、行ってみてはいかがでしょうか」
溜息ばかりついて、ちっとも食がすすまない秋生を見かねたマールさんが、遠慮がちに声をかける。
「ホテル・・・・・・・」
「ええ、ショッピングもお楽しみいただけますし、いろいろとショーなども楽しんでいただけるようになっておりますから」
一人で退屈そうな秋生を気にしての彼の言葉に、一人でいるからこんなに滅入るのだと思った秋生は気分転換にホテルへ行ってみる事にした。
「行ってみます。マールさん、ありがとう」
折角の旅行なのに、暗くなって落ち込んでいるのも馬鹿馬鹿しい。こうなれば一人でも楽しもうと、半分自棄気味に思うのであった。
ホテルはマールさんの言葉どおり、映画館や食事しながらショーが楽しめるようになっていた。
まずはお土産を見ようと、何軒かのお店をゆっくりと見て回った。お金はいつも大概ビンセントが払ってくれるので余り持って来ていなかったため、こんな時にこそ使ってやれと、前々からビンセントに渡されてあるカードを使用した。
いつもなら渋る値段のものも、自分を一人にしたビンセントがいけないのだから少し後悔させてやろうと、買ってしまった。
ショッピングで少し憂さばらして、お茶でもしようと喫茶に入る。ホテルのどこもかしこも豪華な作りで、ゆっくりとした広いスペースに落ちついた雰囲気が漂い、周囲の自然を余すところなく見ることができるようになっている。お客も思っていたよりも遥かに多く、お金持ちって凄くいるもんなんだとしみじみ思ってしまったりした。
もが家族連れかカップルか、グループで来ているようで、一人でフラフラしているのなんて自分くらいではないかと、なんだかする必要のない引け目を感じてしまったり。折角ショッピングで憂さ晴らしをしたのに、少しブルーな気持ちで、ボンヤリと窓から外の景色を眺めながら、秋生は溜息をついてしまった。
(僕ってやっぱり愛されてない?)
こんなにも自分は彼を求めていると言うのに、彼はそうではないのかもしれない。確かに仕事は会社の社長として大切だとは思うけれど、折角の休暇まで台無しにしてしまうなんて、秋生に対する大きな裏切りのように思えてならない。
自分は香港に来て、ビンセントと出会って恋をして、彼がずっと側にいてくれるものだと信じて疑わず、なんとなく日々を過ごしてきてしまったが、もしかしたら、いつのまにかビンセントの気持ちが変わってしまったのかもしれない。
それでなくても、お金持ちでハンサムで有名人な彼の事を狙っている人は、男女関係なく多いのである。最初の頃は、秋生も嫉妬してヤキモキした事もあったが、彼が自分を誰よりも愛してくれている事を信じてきた。
実際、彼は愛してくれていたと思う。でも、心は変わるのだ。自分よりももっと好きな相手が出来たとしても仕方がないのかもしれない。自分には彼のことをずっと惹き止めておく容姿も、才能も何一つないのだから。
(あれっ、僕って駄目じゃん・・・・・・)
今更ながら自分の愚かさを認識するとは、本当に鈍いのかなとブルーな気持ちを灰色に変えて、深く落ちこんでしまった。
(やっぱり、不釣合いなのかな)
庶民なただの学生の自分と青年実業家の彼とでは、生きる世界が違うのかもしれない。愛する気持ちはあったとしても、物に対する価値観、生活感の違いは共に生活するとなると、時として重要な問題になってしまう。
(こんな凄いビーチ・リゾートに絶対に来たいってわけじゃなかったんだ。ただ、ビンセントと一緒だから来てみたいと思ったのに・・・・・・)
確かに興味があり、来たいと望みはしたけれど、二人で一緒に過ごせるからというのが、何より楽しみだったのである。
ビンセントも楽しみだとは言ってくれたけれど、その気持ちは仕事への気持ちよりも小さかったということかもしれない。
泣きたいような切ない気持ちで胸が苦しくなってしまう。
(どうしよう・・・・・・)
このまま来なかったらその疑いは決定的である。その時、自分はもう彼とは一緒にいられないかもしれない。今までのように彼を信じてついていけない。そんな不安な気持ちで彼と暮らしていくのは、無理である。
「すみません、こちら空いていますか?」
突然、声をかけられた秋生は、ハッと自分の暗い思いから引きずり出された。声の主の方を見ると、そこには20代後半の長身の男がたっていた。
胸元が大きくあいた白いシャツに茶色のズボン。手には上着を持っていた。なかなかハンサムな男で、金色の長めの髪を後ろに撫で付け、引き込まれそうな青い瞳には優しげな光が浮かんでいる。日にやけて引き締まった精悍な顔は、爽やかな感じであった。
「きっと誰かとお待ちあわせなんでしょうね。すみません」
黙ったままの秋生の態度に、踵を返して去って行こうとする男の背に、秋生は慌てて声をかけてしまっていた。
「あっ、空いてますから、どうぞ」
急いで買い物の山を足元に移動させて、隣りの席を空ける。店内は、結構人が増えており、確かに空いている席は数少ない。
「ありがとう。すみません」
男は愛想よく笑いながら、秋生の隣りの席へと腰掛けた。
「お恥ずかしい話ですが、昨日の夕方、島に着いてパーティーをしたのはいいんですけれど、飲みすぎたらしく、起きたら昼過ぎてるし、友人達はサッサと海に出かけてしまってて、置いてきぼりですよ。折角、ビーチ・リゾートに来て、なにやってるんだかって感じです」
男は恥ずかしそうに笑って言った。気さくな感じで好感が持てる。
後数時間もすれば日が暮れるだろうし、今から行ってもすれ違いになるだけかもしれない。
「残念でしたね」
「うろうろとホテルで時間潰しをしていたのですが、たまたま入った喫茶で魅力的な貴方と出会えたので、ある意味ラッキーなのかもしれません」
そう言いながら軽くウインクしてくる男のあっけらかんとした態度に、秋生はドキマギしてしまった。
(あれっ、もしかして、僕、ナンパされてる?)
あからさまではあるが、決して嫌な感じはしなかった。
「駄目もとで、どうせなら美人の近くに座れたらなんて思ったのですが、本当に一人なのですか?」
「ええ、まあ、今はですけど・・・・・・」
『今は』を少し強調して言うと、男の顔にやっぱりと言う残念そうな表情が浮かんだ。
「そうですよね。貴方のような魅力的な人が、一人なはずはありませんね。でも、今だけで少しお話していいですか?」
「ええ、それはいいですけど・・・・・・」
「ありがとうございます」
それから二人は自己紹介しあった。
男の名前はキース・ローウェルといい、オーストラリアで牧場や農場を経営していると言う。普段は馬に乗って牛を追っかけているらしく、カーボーイ姿の彼を想像した秋生は、とても似合っているように思った。
「いいなあ。オーストラリアかあ。馬に乗ってみたいなあ」
観光地でちょっと馬に乗った事はあるけれど、本格的に乗ったことは一度もなく、大自然の中を馬で走ってみたいと秋生は興味を抱いた。
「秋生、是非、来てください。大歓迎しますから」
「機会がありましたら・・・・・・」
笑いながら、社交辞令だと思って軽く頷いて流したが、是非にとキースは真面目な顔で言うのであった。
「俺ならきっと貴方に寂しい思いなどさせません。大事にします」
「・・・・・・」
一人でいる理由を正直に話すべきではなかったかなと、秋生は思った。キースの軽い口説きが、マジな感じになってきてしまったのである。その辺が、キースという男の真面目さなのかもしれないが、会ったばかりの彼の誘いにのる気にはなれなかった。
「秋生、もし、よかったら今夜、一緒にディナーでもいかがですか?」
「夕方には連れが来るかもしれませんから・・・・・」
秋生は頭を横に振って、やんわりと断った。
「でも、もし、来なかったら、俺と一緒に過ごしてくれますか?」
「えっ、でも、キースもお友達と一緒なんでしょう?」
なんとか話を誤魔化そうとするが、キースははぐらかされなかった。
「今夜、七時、ここで貴方を待っています。別に約束というわけではありません。貴方の気が向いたらでいいですから」
「御免なさい。多分、来られないと思います」
気まずさを隠せずに、秋生は席から立ち上がり、キースに向かってペコリと頭を下げ、その場から逃げるように立ち去った。
(約束しなくていいからなんて・・・・・・・)
強引でありながら、ちゃんと逃げ道を作ってくれたキースの優しさに、胸がドキドキするのをとめられない。別に好意を持ったとかどうかというのではなく、恋のかけひきに全然免疫がなかったので、マジメに口説かれた事に対して、驚いたのである。
ちゃんと恋人がいて、ラブラブな恋をしているというのに、こういう風なやりとりに余りにも無縁な自分の恋が、とても稚拙な感じがしてしまうのであった。
いっぱい恋をして、いろんな人と付き合ってきたはずのビンセントは、もしかしたら自分といる時間というのを持て余していたというか、余りにも子供子供し過ぎていて、退屈しているのではないかと、秋生は思ってしまうのであった。
(やっぱりもう僕達は駄目なのかな)
連絡もくれないのが、何よりその疑いを裏付けているようにしか思えない。
コテージまで逃げ帰った秋生は、電話を前にして躊躇した。ビンセントに連絡して、自分の不安を決定的なものへとするのが恐くてたまらなかった。
既に向かってきてくれているのであれば、夕方には彼はやって来てくれるだろうし、そうでなかった場合、その理由を彼の口から告げられるのは、自分がまだ彼のことを凄く好きでいるから、凄くショックを受ける事が分かっていたからでる。
ふと気がつけば、空を赤く染めていた夕日が海の彼方に姿を消して、夜空が次第に濃さを増し始めていた。
キースの言っていた時刻がもうそこに迫っていると言うのに、ビンセントからはなんの連絡もない。
(どうしよう)
迷いつつも、秋生は受話器を取って、記憶している東海公司の社長室への直通電話の番号を躊躇いながらも押していた。
トゥルルルル、トゥルルルル
コール音が鳴る。
(出ないで、お願い・・・・・・)
すぐそこまで彼が来ていることを願う秋生であったが、無情にもカチャリと電話が繋がり、愛しい人の声が聞こえてきた。
『もしもし、ビンセント・青です』
「どうして、ビンセント。すぐ来るって言ったのに。何故、来てくれないの」
恨みがましい言葉しか出てこない。追い詰めればそれこそ嫌われてしまうのが分かっているのに、それでも言わずにはいられなかった。
「もう、僕の事が嫌いになったんだね。それならちゃんとそう言ってくれればいいのに。こんな形で終わりを告げられたら、いくら僕でもやっぱり辛いよ。でも、安心して。僕はそれなりに楽しんでいるから。今夜も誘われたし。だから、もう気にしてくれなくてもいいから。無理しなくていいよ」
精一杯の強がりであった。
『秋生、何を言ってるのです?明日には行けると思いますので――』
「もう、嘘はいいから。期待していないから――」
『秋生、ちょっと待ってください、秋生――』
声を聞いているのも辛くなって、秋生は受話器を置いてしまった。
(ビンセントの馬鹿。浮気してやるんだから)
自暴自棄になった秋生の心は、愛する人への恨みで大きく膨れ上がってしまっていた。
時計を見やると、キースの言っていた時間を少し過ぎてしまっていたが、一人、コテージで悶々と過ごすのも堪らなく嫌で、秋生は急いでディナー向けの服に着替えると、コテージを飛び出した。
別に本気で浮気をしようなんて考えてはいないし、キースとディナーを一緒にするつもりもなかった。ただ、一人、コテージで来ない人を待って過ごす事は、今の秋生にとっては堪えがたい時間でしかなかった。
ホテルに辿り着いたのは、キースが待っていると言った時間から、すでに一時間以上も過ぎ去っており、友達と来ているといったし、まさかもういないだろうと思いつつ、とりあえず秋生は昼間に彼と出会った喫茶へと向かってみた。
「えっ」
喫茶の入り口から中をそっとのぞいた秋生は、そこに独り座っているキースの姿を認めて、驚きの声をあげた。
昼間のカジュアルな姿から、ディナー用のフォーマルなスーツ姿へと変わった彼は、ハンサム度を上げており、格好良かった。
(どうしよう、いる・・・・・・)
まさかと思っていた秋生は、自分に気づいてニッコリと微笑み、手を軽く振ってくるキースを今更、無視する事も出来ずに、ペコリと挨拶して、取り繕った笑顔を返した。
「キース、御免なさい。まさか待っていてくれるなんて思ってもなかったら」
慌てて彼のもとに近づきながら、秋生は謝った。
「秋生、来てくれたのですね。実は今夜は一晩中待っているつもりでした。約束したわけではないですが、私は貴方とまた出会えると信じたかったのです。でも、こうして来てくれた。ありがとう、嬉しいです」
爽やかな微笑みでそう告げるキースに、秋生の良心がチクリと痛んだ。
「キース、僕は貴方と過ごす事は出来ません。いくら連れにすっぽかされたからと言って、貴方に甘えるのはとてもずるい事だと思うから」
彼をいい人だと思うからこそ、いい加減なことをして傷つけるような事はしたくなかった。
「いいんですよ。利用していただいても。貴方と一緒に過ごせるだけでも、俺は嬉しいのだから」
大丈夫だからと大きく頷くキースに、秋生は思わず絆されて、心を大きく揺さぶられるのであった。
「キース・・・・・・」
「貴方のような素敵で可愛い人を放っておくつれない恋人の事は、今夜は忘れてください。別に貴方をとって喰おうなんて大それた考えは持っていません。ただ、貴方には笑顔が似合うと思うから。笑って欲しい。それだけです」
「ありがとう、キース。お世辞でも凄く嬉しい・・・・・・・」
「お世辞なんて、俺は言いませんよ。本当にそうだと思うから。秋生はとてもキュートです」
「嫌だなあ、もう・・・・・・」
秋生はずっと重たかった心が少し軽くなったような気がして笑った。
ビンセントとはまた全然違ったタイプではあるが、彼がとても格好いい大人な男に思えた。自分はと言えば、自分の気持ちさえも良く分からなくて、不安ばかりを抱えて、拗ねて見せる事しか出来ない子供のようである。
(まだまだ駄目だなあ)
歳は20を越えたはずなのに、精神的な成長が足りないのは、いつもビンセントという強い保護者に守られているからであろうか。大切にされるのが当たり前になってしまって、彼の気持ちを察せられないくらい鈍くなってしまっていたのかもしれない。
「秋生、もうすっかり腹ペコなんですけど、そろそろディナーでもいかがですか?」
「うん、僕もそうみたい」
秋生とキースは顔を見合わせて笑いあった。
「それでは、行きましょうか?今夜は何もかも忘れて楽しく過ごしましょう」
そう言ってキースが差し出した手を、秋生は、最初は少し躊躇ったが、すぐにしっかりと握り締めるのであった。
折角のビーチ・リゾートに来て、確かに豊かな自然をいっぱい満喫してのんびりもしたが、愛する人と過ごす濃密な時間を期待して楽しみにしていた秋生としては、暗い思いを胸にしたままでこの旅を終わりにしたくはなかった。
もし本当にこのままビンセントと駄目になってしまった時、ちゃんと自分の足で新しい道を歩き出すためにも、もっとしっかりとした自分というのを持たなければならないと思う。
そして、今はとにかく楽しい気分を味わい、気を紛らわせたいのであった。
キースに連れられて、ホテルのレストランへ案内される。そこでは楽しいショーを見ながら、食事が楽しめるようになっていた。
「ハーイ、キース」
「こいつ、何処に隠れてたんだ」
ウエイターに案内されて座った席の向こうから、手を振る四人に、キースがおやおやと溜息をついた。
「一緒に来ている知人達です。賑やかな連中ですけれど、気にしないで下さいね」
「皆、カップルなんだね」
「ええ。俺だけ一人のお邪魔虫って感じなんです」
ハンサムなキースが一人というのが、秋生には疑問に思えてならなかった。
「えっ、信じられない。キース、もてるでしょう?」
「実をいうと、旅行の話が出たときには、付き合っていた相手がいたのですが、その後ですぐに別れてしまったので、一人になってしまいました。でも、お陰様で秋生に出会えましたので、ラッキーだったと今は思います」
「ええーっ」
こんなに優しいキースでも、別れてしまったりするのだから、自分なんて捨てられても仕方ないかもと、秋生は妙な納得をするのであった。
「おいおいキース。何処でこんな美人と知り合いになったんだ」
「もう、心配して損しちゃったわ」
「キャーッ、可愛い。キース、紹介して頂戴」
秋生に興味を抱いたのか、キースの友人達が、二人の座るテーブルへと押し寄せてくる。
「こら、お前達、人の邪魔をするなよ」
冗談まじりで友人達をあしらうキースに、秋生はどうせなら皆で楽しくやりましょうと声をかけた。
「お邪魔じゃなかったかな」
と言いつつ、ちゃっかり席を移動してくる友人達に、キースは苦笑してみせる。
「すみません、秋生。煩かったら遠慮なく言ってください。口は悪いですが、皆、気の良い連中ですから」
「ううん、全然、大丈夫だよ」
「俺としては、二人で過ごしたかったのになあ」
本当に残念そうに溜息をつくキースには、申し訳ないと思いながらも、秋生は二人きりでなくなったのを心の中でホッと安堵した。
いくらビンセントと駄目になったからといって、すぐに次の相手を探すつもりはなかった。というよりは、例えビンセントが自分の事を嫌いになったとしても、秋生は彼の事をまだ愛しているのだ。
キースの友人達と合流して、一気に場は盛り上がった。気さくで楽しい会話を楽しみながら、ショーと料理を楽しんだ。
それからカジノに行って一勝負して、こずかいを稼ぐと、そのお金で皆でバーに飲みに行った。
「本当にラッキーだったわね、秋生。凄いわ」
「ビックリしちゃった。ルーレットであんなに当るなんて、初めてだわ」
軽く何も考えずに賭けたルーレットの数字が、三度もピタリと当ってしまったのである。
「ラッキー・ボーイですね、秋生は」
感心したように言うキースに、秋生はとんでもないと、手を振って否定した。
「ただのまぐれです。僕もビックリ!!」
こんな変なツキがあっても仕方なくて、望むならばビンセントに急に仕事が入って旅行が台無しなんて事にならなかった方が、何倍も嬉しかったりするのになあと、しみじみ秋生は思ってしまう。
「乾杯しましょう!!」
「いいですね」
6人はグラスを掲げ持った。
「楽しい旅と新しい出会いに、乾杯!!」
「乾杯!!」
グラスが合わされて、チーンと小さなを音をたてて、中の液体が揺らぐ。笑顔でそれぞれが子供のように瞳を輝かせてグラスを合わせあって、心から乾杯した。
会って間もない人達の中で、秋生はこのビーチ・リゾートを訪れて始めての喜びを感じていた。確かに落ち込みもしたけれど、その分、こうやって新しい知り合いが出来たのである。例え、それが一時であり、島を出たら二度と会う事はないかもしれないけれど、今この時を一緒に過ごしたという想い出は、一生の宝物になるだろう。
日本にいるときは平凡な普通の生活を送っていたけれど、香港に来て、ビンセント達と出会い、自分が黄龍の転生体と分かってからは、いつも自分の側には四聖獣達がいてくれた。
その日々はそれなりに楽しいものであったが、何処か普通とは違う、今までの人との繋がりが変わってしまったところもある。
このまま、ビンセントと別れる事になっても、きっとビンセントは四聖獣の青龍としての務めを果たすべく、秋生をずっと影ながら見守ってくれるだろうけれども、こんなビーチ・リゾートで優雅に過ごすなんて事は、きっともうないに違いない。
楽しさについつい話し込んでしまった一同が、時間に気づいたのは、もう深夜も過ぎて、明け方まで数時間という頃であった。
「本当に楽しかったわ」
「また、明日っていうか、昼にはまたビーチで会いましょう」
「おやすみなさい」
皆をコテージのプライベート・ビーチに招待したのである。すっかり仲良くなった秋生を、彼女達は抱き締めて、頬にお別れのキッスをしてくれた。
「コテージまで送ります、秋生」
「キース、大丈夫だよ」
「いいえ、きっと一人で帰したりしたら、心配で眠れませんから」
「すみません、ありがとう」
優しい言葉に素直に甘える事にした。
おやすみなさい、また明日と皆と手を振って別れの挨拶をして、秋生はキースと共にホテルを出た。
夜風はさすがに涼しくて、少し酔った身体には丁度いい感じであった。
人気のない道を二人でゆっくりと歩きながら、秋生は満天の星にホーッと感嘆した。
「凄いね。こんなの日本でも、香港でも見えないや」
「俺の所も自然に囲まれてますからね。牛を追って何日も野宿する事もあって、その時には夜空を眺めてますよ」
「やっぱり来て良かったな。自然がこんなに美しいって事、分かっていたつもりで、なんだか大切な事を忘れていたような気がします」
そう言って笑った秋生をキースは眩しげに見つめた。
「やっぱり貴方は笑顔が似合います」
「ありがとう、キース。僕、なんだか元気が出ました。自分の中の不安に振り回されて、自分の気持ちがどうなのか見失いかけていたのかもしれません」
キースはきっと分かってくれるだろうと、あえて秋生は思ったことを口にしてみることにした。
「彼を信じたいけど、信じきれなくて、きっともう自分達は駄目なんだという不安に押し潰されそうになって、もう待っているだけの自分は嫌だと思って、逃げ出したくなってしまったんです。なんだか自分って全然駄目な使えない奴に思えて、そんなだからきっと彼にも嫌われたんだなんて思ったりして」
「秋生・・・・・・」
キースは秋生の言葉を真剣な表情で聞いてくれていた。
「でも、僕はやっぱり彼の事を好きだから、その気持ちを大切にしたいなって思いました。例え別れる事になっても、僕の気持ちは変わらないかなって・・・・・・。そんな簡単な事に気づかなくて、彼のことを恨んでみたりしました。本当に僕ってつまらない奴だったりして。でも、キースや皆が、僕なんかに凄く優しくしてくれて、なんだか元気をいっぱいもらっちゃって、元気が出ました。こんな僕でもいいのかな、一人でも頑張れるかなって、勇気が出ました」
「秋生・・・・・・」
いきなりキースに抱き寄せられて、その腕の力強さと胸の暖かさに、秋生はアッと動揺したものの、抵抗忘れて、その腕に身を委ねた。
「貴方はやっぱり素敵な人だ。どうしてその男よりも先に貴方に出会わなかったのでしょう。俺も此処に来る少し前に、ずっと学生の頃から付き合っていた彼女と別れました。彼女とはその内に結婚するんだろうななんて、考えてたりしましたが、彼女は仕事を選びました。俺も自分の仕事に誇りを持っていますから、その気持ちは分かるし、別に結婚という形で彼女を縛るつもりはなかったのですが、結局は分かれてお互いに自由になってみようという事になりました。その方が仕事に集中出来るからと彼女に言われたのは、はっきり言ってショックでした。人の想いってなかなか伝わらないものですね。言葉にしても、文章にしても意味の取り方で全然違った解釈になってしまう。どんなに人々が幸せを願い、平和を唱えても、戦争が起きてしまうように。お互いが自分達の利益だけを追求した主張しかしないから、話はいつまでも平行線で交じり合う事が決してない。少しでも歩み寄ろうとする気持があれば、不幸な事態には決してならないはずなのに、そんな簡単な事が出来ないのです」
静かに語るキースの口調に彼の心の苦しみが垣間見えて、秋生は切なくて、思わず彼をギュッと抱き締めていた。
「キース、貴方はとても優しい人ですね。少なくとも僕は貴方に出会えてよかったと思います。きっと彼女は貴方が素敵な人だから、自分のために貴方を反対に束縛したり、辛い思いをさせるのが嫌だったのかもしれません。僕はそんな風に思います」
「ああ、秋生、ありがとう・・・・・・」
キースの声が涙に震えていた。大人の包容力で秋生の苦しみを包んで癒してくれた彼もまた、心に傷を負っていたのである。その痛みを知っていたこそ、キースは優しくしてくれたのかもしれないと、秋生はしみじみと思うのであった。
「秋生!?秋生ですね!?そこで何をしているのです!!」
突然、暗闇からかけられた声に、二人はハッとして身構えた。
「こんな時間まで一体何処にいたんです?」
問い詰めるような厳しい声の主は、ずっと秋生が待ち続けていた人であった。
「ビンセント!!」
(どうして、ビンセントがいるの?香港じゃなかったの?)
驚きを隠せない秋生の側に、いつものきちんとしたスーツ姿のビンセントはツカツカと歩み寄って来ると、キースの腕の中にいる秋生を厳しい表情で睨みつけ、乱暴に腕を取って、強引にキースから引き離し、自分へと引き寄せた。
「痛っ、痛いよ、ビンセント」
かなり強い力で掴まれた腕が痛くて、秋生は声をあげたが、聞き入れてはくれなかった。それどころか、彼の余りにも冷たい眼差しに、秋生は彼の怒りの深さを感じ取った。
(ビンセントが凄く怒ってる!?)
怒りたいのは自分の方なのに、何故、こんな乱暴な事をするのか、秋生には理解出来なかった。
「送っていただいて、ありがとうございました。もう、大丈夫ですので、どうぞお引き取りください」
刺のある言葉であった。彼がここまで相手に対してあからさまな敵意見せるのは珍しかった。
「分かりました、秋生、おやすみなさい」
「キース、御免なさい。ありがとう」
「おやすみなさい、また、明日」
ビンセントの不躾な態度に気を悪くした様子もなく、キースは秋生に微笑むと手をあげて挨拶して、去っていく。
その間もビンセントの束縛は、解かれることはなく、冷ややかな瞳でキースを見つめるビンセントが、静かに怒っている事だけは分かった。
「痛いよ、ビンセント。離してってば・・・・・・」
秋生の気持などどうでもいいかのようなビンセントの態度に理不尽なものを覚えてムッとした秋生は、身を捩って彼に訴えた。だが、便箋との束縛は緩むどころか、冷たい問いが返ってきた。
「秋生、あの男はなんですか?」
「キースとは、昨日、ホテルで知り合ったんだ」
「貴方はいつから知り合ったばかりの男と、抱き合うような方になってしまったのですか?」
その冷たい声に、秋生は身を震わせた。
「抱き合ってなんかないし、彼は良い友達だよ」
「私はこの目で見ました。貴方があの男と抱き合っているのを、しっかりとね。嘘は結構です」
その余りのいいように、秋生は例え様のない悲しみと怒りを覚え、思いっきり彼に体当たりして、彼の腕の中から逃げ出したながら、訴えた。
「なんだよ、嘘つきなのはビンセントの方じゃないか。すぐに行きますなんて言っておきながら、全然来ないし。連絡もして来なかったじゃないか。それなのにどうして僕の事を嘘つきなんていうの。僕の事が嫌になったんだったらはっきりそう言えばいいんだ」
「何を言っているんです」
ビンゼントの不機嫌そうな表情に、秋生は自分の言った言葉が図星だからこそ、彼は何も否定しないのだと思うのであった。
「もういいから。僕の事なんか気にしてくれなくてもいいから。ビンセントは好きにすればいいんだ。僕もそうするから!!」
怒りが先に立って、自分でも何を言っているのか分からない。
「好きにするって、あの男を貴方は選ぶというのですか?この私よりも」
「そうだよ」
そんな気はさらさらないというのに、意地っ張りな心は冷たいビンセントに対する怒りで勝手に暴走してしまう。
「キースはとても優しくしてくれるもんね」
「貴方は、優しくされればホイホイと誰にでもついて行くのですか?」
自分が引き出したビンセントの言葉であったが、熱くなった秋生には、とてつもない嫌味な言葉に思えて、一気に怒りは倍増してしまうのであった。
(なんだよ、ビンセントの馬鹿。どうして、そういうこと言うの?信じられないよ!!)
「どうせ僕は尻軽だよ。寂しい時に側にいて優しくしてくれる人の方が、仕事馬鹿で冷たい嘘つきなんかより、何倍も大好きさ!!」
バシンッ
という音共に、秋生は頬に痛みを覚えて、目の前がくらくらするのを感じた。
「な・なんで殴るのさ。ビンセントの馬鹿!!」
痛みと情けなさに思わず涙が零れて落ちるが、その涙を拭うのも悔しくて、秋生はビンセントを睨みつけた。
「自分の思うようにならないと、暴力をふるうんだ。見損なったよ、ビンセント。最低だよ!!」
必死な秋生に対して、ビンセントはあくまでひややかだった。
「すこし頭を冷やしなさい。自分が何を言っているのか、分かっているのですか?」
その態度は秋生を煽るだけであった。
(どうしてそんなに冷静でいられるの。本当に僕の事なんかもうどうでもいいと思っているんだ)
不安が確信に変わり、秋生は絶望に襲われて、涙をポロポロと流した。
さすがにそれはビンセントを動揺させたらしい。そっと近寄って秋生の方へと手を伸ばしてくるが、秋生はその手をパシッと払いのけていた。
「もう終わりだね、僕達」
そう吐き捨てるように言うと、秋生はくるりと踵を返して、走り出した。
このままビンセントといたら号泣してしまいそうだったからだ。
「待ちなさい、秋生!!」
駆け去る秋生の後姿にビンセントは声をかけたが、軽く無視されて、彼はギュッと拳を握り締め、慌てて秋生の後を追うのであった。
ハアハアッと荒い息を吐いて、秋生はたまらず立ち止まった。もうここまでくればビンセントも来ないだろうと思って、後ろを振り返ると、暗闇の中に追いかけてくる彼の姿を発見して、慌ててまた走り始める。
(なんでついてくるんだよ。放っておいてくれればいいのに)
冷たくしておきながら、一人になりたい時にはそれを許してくれない彼の気持が秋生には最早理解出来なかった。
(優しくされれば誰でもいいだなんて、酷すぎる)
思いがけない彼の言葉。それが本心だとしたら、自分はやはりとっくに見捨てられていたに違いない。仕事が忙しいなんて単なる理由で、実は会いたくなかっただけなのかもしれない。
グルグルと不安が頭の中を過ぎり、それから逃げたくて、秋生はがむしゃらに走っていた。
「あっ!!」
足元を何かに取られて、秋生はバランスを失ってそのまま前へと躓いた。無謀の体勢で地面に叩けつけられると覚悟したが、幸いな事に下は柔らかな砂地であった。
安堵したもののハアハアッと荒い息を吐きながら、余りにもついてない自分が悔しく思って、手元の砂をギュッと握り締めた。
「大丈夫ですか?」
すぐ近くまで来ているビンセントの声に驚いて、秋生は慌てて上半身を起こして、後ろを振り返った。
そこには息も切らさが相変わらず冷たい美貌を微塵も乱していないビンセントが立っていた。
「何故、逃げるのです」
近づいてきた彼は手を差し出して、秋生が立つのを助けようとするが、秋生はその冷静さが気に障って、掴んでいた砂をスーツ姿の彼へと投げつけていた。
「来ないで!!ビンセントなんて嫌いだ!!」
「何を子供みたいな事を言っているんです」
ビンセントは躊躇う事無く嫌がる秋生の腕を掴むと、そのまま自分へと引き寄せた。
「嫌だ、放して!!」
必死でもがく秋生であったが、ビンセントはしっかりと自分の腕で秋生の身体を捕らえてしまうのであった。
「もう抱かれたのですか?そんなにあの男の方が良かったですか?」
自嘲気味に秋生の耳元で囁くようにビンセントに、秋生は違うと頭を大きく横に振った。
「そんな事するもんか。このわからずや」
情けなさに涙がまた溢れてきて、秋生は思いっきりビンセントの頬を打っていた。
「そんなに僕の事が信じられないんだ。そうだよね。優しくされれば誰でも良い尻軽だと思っているんだもんね。いいよ。そう思えばいいさ」
自暴自棄になって叫び、彼の元から少しでも逃げようと試みるが、ビンセントの動きの方が素早く、忽ち腕をとられて、再び躓いてしまう。
(どうしてこんなことになっちゃったんだ)
この旅行をどんなに楽しみにして待ち焦がれていた事か。それなのに裏切ったビンセントに責められて、理不尽な思いに秋生は悔しさを隠しきれずに、倒れたまま砂地を拳で打って声を殺して泣いた。
南の島の美しい自然の中で、何故、自分はこんなに惨めにならなければならないのだろうか。
「秋生・・・・・・」
ビンセントが側に近づいてきたが、もう逃げる気力も失っていた。
「本当に違うというのなら、私を納得させて下さい。他の男と抱き合っている姿を見せられ、ショックを受けた私の疑惑を晴らして下さい」
「どうせ信じないくせに」
「私を信じていないのは、貴方も一緒ですよ。秋生」
「なんで居直るんだよ。約束を守らないのは、ビンセントの方じゃないか。勝手なことばかり言わないでよ」
頭を上げて睨みつけた秋生の顎を、ビンセントの手が捉えて、強引に口づけてくる。
「や・嫌っ・・・・・・」
砂地にそのまま押し倒されて、動けなくなった秋生は、ビンセントの背中を叩いて抵抗してみるが、ビクともしなかった。
「んんっっ・・・んっ」
口腔を思う存分蹂躙されて、秋生の息はすぐにあがってしまう。嫌だと思うのに、暫くぶりの甘い刺激にならされた身体は、より強い快感を求めて疼きだすのであった。
「んっ・・・ああっ、嫌っ・・・」
口づけの間に、ビンセントは手際よくシャツのボタンを外すと、秋生の胸を露にして、手を滑らせてその滑らかな肌の感触を味わう。そして、胸の突起をわざと乱暴に摘まんで、秋生の反応を確かめた。
「ああっ・・・んっ」
ピクッと身体を反らせて、喘ぐ秋生。
「誰にも触らせていませんね」
コクコクと頷く秋生の頬が、暗闇でも羞恥に赤く染まっているだろう事を、ビンセントは感じた。
「それでは、ここはどうですか」
手をゆっくりと滑らせて、ズボンの上から秋生の股間に触れてみる。
すると先程よりも大きく身体を反らせて、ビンセントの背中にしがみついてきた。
「はしたないですね。もう、こんなに感じていますよ。本当に誰にも触らせていませんね」
「触らせて・・・ないよ。ビンセント・・・だけだよ」
喘ぎながら、潤んだ瞳で切なげに見つめてくる秋生に、ビンセントは『いいでしょう』と大きく頷いてみせた。
そもそもビンセントは秋生が浮気をするなんて事があるはずがないと信じていた。
ただ、さすがに今回ばかりは秋生に寂しい思いをさせてしまったという負い目があった上に、かかってきた電話の様子が余りにも変だったので、少々焦ってしまったのは確かである。
それは出発する当日の事。出先から一度会社へと戻ろうとしたビンセントの乗った車が、事故に遭ってしまったのである。無免許運転の車がセンターラインをオーバーして、彼の乗った車へと追突してきたのだ。
運転手が咄嗟にハンドルを切ったお陰で正面衝突を回避し、端をこすって、ガードレールへ当っただけですみ、ビンセントは、怪我もなく事なきを得たのだが、同乗していた秘書の廖が、怪我を負ってしまった。
外傷はたいしたことはなかったが、頭を強く打ったらしく、なかなか意識が戻らなかったのである。おまけに、回復したもののそんな状態の廖をすぐに働かせるのも忍びなく、とりあえず仕事を片付けてからと思ったのだが、そう言う時ほどどういうわけか、次から次へと問題が起きたりして、なかなか脱げ出せなかったのである。
ビンセントとしても、秋生が旅行を楽しみにしていたのを知っているので、中止などにしたくなかったし、もっと早くに来られるつもりではあったのだ。
だが、さすがに秋生の怒りの電話を受けて、結局、廖に自分のせいで二人の仲とんでもない事になるのは困ると言われて、飛び出してきたのである。
そして、コテージに辿り着いたものの、秋生の姿はなく、待っても待っても帰って来なくて、心配になって探しているところで、秋生が見知らぬ男と抱き合っている姿を見てしまい、頭に血が上って、責めてしまったのであった。
普段は冷静な自分を、こんなにも動揺させ、乱れさす存在は秋生だけであった。
優しく大切にしたいと思っているのについついきつくあたってしまうのは、秋生が余りにも無防備過ぎるからである。
「愛しています、秋生」
何度も何度も繰り返しそう告げてきたが、その言葉が少しも秋生に伝わっているように思えない。言葉だけではもう足りないのである。この自分の中に熱いマグマとなって燃え盛っている塊を吐き出してしまわないと、狂ってしまいそうであった。
「あんっ・・・んっ・・・いいっ」
夜とはいえ打ち寄せる波の音をBGMに砂浜に押し倒されて蹂躙されているというのに、身体はビンセントの愛撫に熱く燃え、もたらされる快感の虜になって、秋生はひたすら喘ぎ続けた。
遠慮なく秘部を犯して突き上げては、ギリギリまで引き抜かれてまた内部へと侵入してくるビンセントに、感じるところを思いっきり突かれて、秋生は忽ち絶頂をむかえる。
「あっ、いい・・・いっちゃうよ、ビンセント」
「ああ、秋生、愛してします」
「あんっ、僕も、愛して・・・る・・・ああっ」
身体がトロトロに解けて、頭が真っ白になって何も考えられなくなる。ただ、分かっているのはビンセントを愛しているということだけであった。
「ああんっ」
一際大きなよがり声をあげて、秋生はってしまう。それと同時にビンセントも秋生の中で果て、二人は全身を駆け巡る快感に浸り、幸せを感じながらキスを交し合うのであった。
つづく
トップに戻る