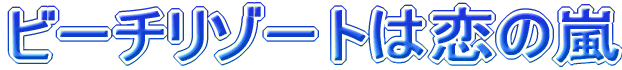
2006年3月4日
(2)
ザザーン、ザザーン
静かな波音が聞こえてくる。
泳ぎ疲れた後の、心地よい疲労がもたらす浅い眠りの波間を、僕はユラユラと漂っていた。
もっと眠っていたいと思うんだけれど、閉じた瞼の向こうの明るい世界の気配が強くて、僕の意識は急速に目覚め始める。
「うーん・・・・・・」
眠ったはずなのに、身体の疲れが少しもとれてないのはどうしてなんだろうと思いつつ、少しでも楽になろうとして、僕は縮こまっている身体をほぐそうと、無意識に身体を伸ばした。
(あれっ・・・・・)
特に下半身がだるくてたまらない。その理由をぼんやりと考えていたら、やっと頭の脳細胞も動き出したみたいで、急に昨夜の出来事が鮮明に蘇ってきて、僕は思わず赤面してしまった。
(ぎゃーっ、僕ったら信じられない・・・・・・)
真夜中のプライベート・ビーチでとはいえ、浜辺で獣のように淫らなHをしてしまったのだ。
それも最初は一方的に押し倒されるという、自分の意志とか感情とかを一切無視された形であったのにもかかわらず、凄く感じて彼に縋って喘いでしまった自分が、とてつもなく淫らな人間のように思えてしまう。
ビンセントとそういう間になってから、幾度となく身体をつないできたけれど、あんなに屈辱的でありながら、とても刺激的だったHは、そんなにはない。いつもの彼はとても紳士的で優しいから。
それは別に普段の行為に満足していないというのではなくて、僕がこのビーチ・リゾートに来て、知り合いになったキース・ローウェルに送られて帰ってきたところを見て、僕が浮気をしていると勘違いして怒ったビンセントの、普段決して見せることのない荒々しくて、逞しい姿というか、僕を凄く愛してくれているんだという事を実感出来たからというのが、そう感じた本当の所だと思う。
だって、折角豪華なビーチ・リゾートに来たにもかかわらず、ずっと一人で待ちぼうけをくっていたのだ。寂しくて、不安でたまらなかった。
もう、ビンセントの心が僕から離れてしまったのではないかとまで邪推して、『浮気してやる』なんて、自棄おこしたりしてしまった。でも、実際、そんな気はさらさらなく、僕の事を好きだと言ってくれたキースにも、ハッキリと断った。
キースはとてもいい人で、そんな僕の弱い心を知って、相談にのったり、励ましてくれたりした。彼の優しさにつけこんで寂しさを紛らわしている自分が卑怯に思えたりもした。
(あれっ、ビンセント、何処?)
隣りで眠っているはずのビンセントの姿を捜したが、寝室にも、バスルームにもいる気配はなかった。
結局、昨夜は欲望の虜になった僕達は、浜辺でHした後、砂だらけになった洋服を脱ぎ捨てて、二人でシャワーを浴びて、そこでも愛しあった。それから、ベッドになだれ込んで、もう一戦。
最後に僕は彼の腕の中で気を失う明け方まで続いた、とても濃密で甘い二人きりの時間に、心も身体も酔いしれてしまった。
(でも、幸せかも・・・・・・)
Hの間に、どうしてすぐに来なかったのか、その理由を聞いて、僕は自分がいらぬ心配をしていた事を後悔したし、今度の旅行を心待ちにしていた僕の気持ちを知っていたからこそ、廖さんが怪我した事を話すと、僕がきっと旅行を取りやめにしようと言うだろうと考えて、あえて僕にちゃんと理由を話してくれなかったのかも理解できた。
確かにそんな大変な事を聞いたら僕はそうしていたと思う。廖さんはビンセントの会社の大切な秘書だけど、僕個人にもとても大切な人だ。僕の愛するビンセントを支えてくれているのだから・・・・・・。
僕はバスローブを羽織ると、ビンセントの姿を捜して、寝室を出た。
(あっ、みっけ!!)
彼はリビングから出た、テラスのテーブルの前に座っていた。この常夏の島だというのに、きっちりとアイロンのかかったシャツにしっかりネクタイまでしたいつもの姿で、汗などかかずにあくまで涼しげな様子で、電話をしている。きっと仕事の話だというのは分かったけれど、僕の心は寛大である。来てくれただけでも嬉しいから。
彼は真面目な顔をして電話していたけれど、僕の姿に気がつくと、フッと微笑んでくれた。
それだけでドキンと心臓が高鳴る。僕は焦って手なんか振ってみた。なにやっているんだろうって感じ。今更照れたところで仕方がないのにね。
さすがに手を振り返してはくれなかったけれど、変わりにウインクが飛んできて、爆死。って事にはならなかったけれど、心臓はもうバクバク破裂寸前。
(こんなに毎日、好きになれるんだね)
好きっていう気持ちって、新鮮さがなくなると薄れてしまうのではないかなんて考えて焦った事もあったけれど、
実際は全然そうじゃない。ちょっとした仕草とか言葉にドギトキときめいてしまう。それはやっぱりビンセントがそれだけ魅力的だという事なのかもしれない。
(ビンセントも僕の事そうだといいのに)
そうあって欲しいと願っている。でも、とりあえず僕の事、凄く愛してくれている事は昨夜、確認済み。
僕はテラスに出ると、電話しているビンセントの頬におはようのキスをした。
さすがにビンセントも一瞬、言葉を失ってしまったみたい。
(へへへ、やったね)
悪戯心が満たされて、してやったりとニンマリ笑って、その場を離れようとしたら、手をつかまれて、チョンとビンセントの膝の上に座らされてしまった。
(あれっ?)
なんだろうと思う間もなく、バスローブの裾が割られて、受話器を持っていない左手がスルリと滑り込んできたかと思ったら、スーッと太ももの内側を撫で上げて、股間へと接近してくる。
その手の微妙なタッチがなんともいえず、ザワザワと甘い感覚が身体を走り抜ける。そして、股間をキュッと握りこまれて、僕は慌てギャーッと彼から慌てて離れた。
(もう、ビンセントのスケベ!!)
自分から挑発しておきながら、経験値の差から完敗してしまった悔しさにキッと睨みつけると、彼は相変わらず真面目な顔をして電話で仕事の話をしながらも、僕の方を見て涼やかに笑った。
そこへ、朝食を持った執事のマールさんが姿を見せた。危機一髪。さすがにあんなところは見られたくはない。僕はバスローブの乱れを慌てて直すと、何もなかったようにマールさんに笑って朝の挨拶した。
「マールさん、おはよう」
「おはようございます、秋生様。ミスター、ビンセント・青がお越しになって、ようございましたね」
「うん」
僕は素直に頷いた。本当にそう思う。マールさんにも気を使わせてしまったに違いない。
「夕べ、遅くに来たから、もうビックリしちゃった」
「それだけ早く秋生様にお会いになりたかったのだと思いますよ」
「心配してくれて、ありがとう、マールさん」
彼の言葉が、嬉しかった。
「あっ、マールさん。午後から友達が遊びに来るんだ。夕方、皆でバーベキューパーティーしようって事になってるんだけど、用意してもらえますか?」
すっかり忘れてしまっていたけれど、昨夜、キースと一緒に来ているテリーとアン、エドとキャシーの二カップルとすっかり仲良くなって、僕が泊まっているコテージのプライベート・ビーチも一人では寂しすぎるから、皆を招待していたのである。
「バーベキューパーティーですか。それは楽しゅうございますね。勿論、ご用意させていただきます」
「お願いします」
「はい、承知いたしました」
マールさんは、テーブルにコーヒーとパン、スクランブルエッグにロースハムと果物の皿を、テーブルに手際よく並べると、『御用があればいつでもお呼びください』
と、言い残して去って行った。
僕はビンセントと向かい合うようにテーブルに座った。さすがにお腹が減っている。
そして、やっとビンセントも電話が終わったみたいで、受話機をテーブルの横のボードの上に置いた。
「バーベキューパーティーの事は聞いていませんよ。秋生。一体、誰とするつもりなのですか?」
僕だってマールさんに会うまではすっかり忘れていたのだから、ビンセントが知っているわけはない。
「だって昨日、約束したんだもん。まだその時は、ビンセント来てなかったし。きっと一人きりで寂しく過ごさなくちゃいけないのかと思って、皆を誘ったんだよ」
「昨夜のあの男も来るのですか?」
ビンセントの言葉に刺を感じて、僕は焦ってしまった。
「キースとそのお友達の四人とだよ。ホテルで会って、仲良くなったんだ」
下手に隠すとかえって怪しまれるので、僕は本当の事を言った。
「皆、僕が一人だったから心配してくれて、遊んでくれたんだ。ビンセントも会ったら皆にお礼を言ってね」
「・・・・・・」
『一人だった』を強調して言うと、返事はなかったけれど、とりあえず反対もされなかったので、不承不承ながらもとりあえずオーケーかなと、僕はホッと一息をついた。
「僕もう、腹ペコだよ」
またいろいろと突っ込まれると厄介かなと思って、話を強引にそらして、『いただきます』と手を合わせると、僕は目の前に並んだ料理を食べ始めた。
ブランチが丁度終わった頃、コテージの玄関のベルがなった。慌てて出てみると、テリーとアン、エドとキャシーだった。
「こんにちは、秋生。素敵なコテージね」
「こんにちは、アン」
「お招きありがとう、秋生」
「ようこそ、キャシー」
僕は女性二人と挨拶を交わした。テリーとエドは、飲み物や、ビーチパラソルや浮き輪など、手にいっぱいの荷物を持たされていたので、笑顔で挨拶した。
「あれ、キースは?」
僕はキースの姿が見えないので変に思って、何気なく尋ねたのだが、四人は顔を見合わせると、気まずそうな顔をした。
「後で遅れてくると思う」
「ちょっとね。意外な人とホテルのロビーで会っちゃって。少し話をしてから来るって」
「私達もまさか彼女とこんな形で会うなんて思いもしなかったわ」
「ちょっと、酷いよね」
話が全然見えてこなかったけれど、キースに関わる事が何かあったという事だけは分かった。
(大丈夫かな、キース)
そこへ、さすがにシャツにネクタイじゃまずいからと、白のポロシャツと茶のズボンというカジュアルな服に着替えたビンセントが、お客様を迎えるために出て来てくれた。
「こんにちは、始めまして。ビンセント・青です。秋生がお世話になったそうで、どうもありがとうございました」
爽やかな笑顔で挨拶する姿は、さすがに普段、社長として洗練された立派な態度だと思う。
アンもキャシーも、うっとりして頬を赤く染めて、握手している。テリーとエドは、慌てて荷物を地面におくと、緊張した面持ちで挨拶していて、僕はなんだかおかしくなって笑ってしまった。
(ビンセント、猫かぶってる)
でも、僕のためにそうしてくれているんだと思うと、凄く嬉しい。
「さあ、どうぞ」
ビンセントに中へと進められて、四人はなんだか緊張して、僕の方へ救いを求めるような視線を送ってくる。僕は彼らに『どうぞ』と笑って、中へ入るように進めると、四人はやっと中へ歩みを進めた。
「うわぁっ、素敵」
「ここって、凄くお高いんでしょう?それにいつも予約でいっぱいでなかなか取れないって聞いてます」
ホテルとコテージとでは、一泊の宿泊料だけでもかなりの差があるらしい。
「ここのオーナーと知り合いで、今回は招待してもらいましたので、よく分からないのですが」
「ええーっ、凄―いっ!!」
女性二人はもう素敵とばかりに、ビンセントにあれこれ質問を始めてしまう。
なんだか面白くない顔をしたテリーとエドに、僕は飲み物を勧めながら、話し掛けた。
「キース、どうかしたの?」
二人は複雑そうな表情を浮かべて言った。
「ここへ来る前にキースの別れた彼女のリサと、ホテルのロビーでばったり会ったんだよ」
「彼女、務め先の社長と一緒でさ」
僕は、先程のアンとキャシーが『酷い』といった意味をなんだか察してしまった。
確かキースは、この旅はもともと彼女と来る予定になっていたと言っていたはずである。別れたばかりで、その相手が他の男と旅行に来ていると知ったら、それはかなりショックだと思う。
「俺達、学生時代からの知り合いだけれど、リサがこんな酷い事する人だとは、ちょっと思わなかったよな」
「ああ、キースは別にリサが嫌いになったから分かれたわけじゃなくて、彼女がどうしても仕事を優先したいって望むから、彼女の夢の為に自分の気持ちを抑えて、別れたのにさあ。他の男と、約束していた旅行に来るなんて、神経疑うよな」
「ええっ、それじゃキース、かなりショックなんじゃ」
僕は彼の事が凄く心配になってしまった。僕の弱い気持ちを理解してくれて、励ましてくれた彼は、きっと自分もそういう痛みや苦しみを知っていたからなのかもしれない。
「ロビーで、リサの姿を見てさ。真っ青な顔してたな。キースって割に自分の感情を表に出さないほうじゃない。それだけに凄くショックを受けているのが分かるくらいだったから、相当だと思う」
「俺だって、別れた彼女が自分と約束していたはずの旅行に、他の男と来ているのを見たら、冷静ではいられないよ」
(僕だってそうだよな)
もし、そんな事になったら、怒るか泣くか、それは大変だと思う。別に相手が好きじゃなかったらショックなんか全然受けないだろうけど、好きだからこそなんで自分ではなくて他の人間なんだと憤りもするのだ思う。
(キース・・・・・・)
あんなに素敵な人に、そんな辛い思いをさせるリサという女性が、僕は許せないと思った。よりによって一緒にくるはずになっていた旅行に、他の男と来るなんて絶対に信じられない。
その時、玄関のチャイムがなって、ハッと我に返った僕は、慌てて玄関へと出て行った。
「キース!?」
「ハーイ、秋生。今日はお招きありがとう」
笑顔のキースが変わらぬ様子で立っていた。
「キース、遅いよ」
僕も何も知らないふりをして、彼を迎えた。
「悪かったね。出かけに知り合いに偶然、会ったものだから」
「そう・・・・・・」
そこで彼は急に小声になって僕にそっと身を寄せてきた。
「昨夜、彼とはちゃんと仲直り出来たかな?」
こんな時にまで僕の心配をしてくれる彼の気持ちが嬉しくて、僕は素直にコクリと頷いて、囁いた。
「おかげさまで、少し苛められちゃったけど・・・・・・」
「それは、それは・・・・・・。良かったね」
「ありがとう」
オホンと後ろでビンセントの咳払いが聞こえて、僕は慌ててキースから離れた。そんな僕にチラリと冷たい視線を寄越しつつ、ビンセントがキースに歩み寄った。
「昨夜は大変失礼しました。秋生が大変お世話になったそうで、どうもありがとうございました。ビンセント・青と申します」
「こちらこそ失礼いたしました。キース・ローウェルです」
ガッチリと笑顔で握手する二人に、僕はホッと安心した。
本当はキースが別れた彼女と会って、どんな話をしたかとか凄く気にはなったけれど、キースが何もなかったように振舞うのは、今はその事に触れて欲しくないと思っているのかもしれないと感じたので、僕はあえて聞くのはやめた。
それから僕達はすぐにビーチへと出かけたけれど、ビンセントは気を利かせてくれたのか、仕事があるからといってコテージに残ったので、僕達6人は、泳いだり釣りをしたり、カップルでビーチバレーの対戦をしたりと、子供のようにはしゃいで楽しんだ。
そして、仕事を片付けたビンセントは、頃合を見計らって、マールさんと一緒にバーベーキューパーティーの用意をしてくれて、その手際のよさに、こんな隠れた才能もあったのかと感心してしまった。新鮮な魚介類と肉の豪華なバーベキューに、誰しもが目を見張ってしまったほどだった。
おもえばいつもは料理の専門家であるヘンリーが仕切ることがほとんどで、ビンセントが料理をする姿なんてお目にかかったことはなかったので、僕にはとても新鮮に感じられてしまった。
(旅行に来て、よかったな)
一人で来て不安になって、いろいろ悩んだりしたけれど、それはそれでやっぱりビンセントの事が凄く好きで、大切な存在なんだという事を改めて確認する事が出来たので、決して無駄ではなかったと思いたい。
(僕はこんなに幸せなのに・・・・・・)
変わりない笑顔で話しているキースが、それでも時折、何か思いつめたような寂しそうな表情を浮かべているのを、僕は見逃せなかった。
(キースにも幸せになって欲しいよ)
だからといって、事情をよくしらない僕が何か出来るはずもない。けれども願わずにはいられないのであった。
バーベーキューパーティーは盛り上がり、海と空を夕日が真っ赤に染め始めた頃に、お開きにする事にした。
でもこれで終わりではない。二次会は、昨日遊んだホテルのカジノで、そこで遊んでからまた飲もうという話になった。
こんなに遊んでばかりでいいのかと思うけれど、遊ぶためにわざわざ来ているのだから、遊ばなきゃ損って感じである。
「それじゃ、また後で」
「はーい、後でね」
後でホテルで待ち合わせることにして、僕とビンセントは皆を見送った。
「ビンセント、ありがとう。バーベキュー凄く美味しかったよ。皆も喜んでくれたし、僕も凄く楽しかったし嬉しかった」
コテージに戻った僕は、ビンセントにお礼を言った。勝手に決めた僕の予定にちゃんと付き合ってくれて、皆にも優しく振舞ってくれたからだ。
「いいえどういたしまして。貴方のためでしたら大した事ではありません」
そういう恥ずかしい事を平然と言ってくれるのだから、本当に幸せ者である。
僕はお礼にと思って、ビンセントの首に手を回すと、彼の唇にキスした。それはちょっと軽いつもりであったのに、身体を離そうとしたら反対に抱き込まれて、深く口づけられてしまった。
あっという間に舌が歯列を割って侵入してきて、口内を思うままに貪られてしまう。その甘さに僕は酔いしれて、僕も思う存分楽しんだけれど、その内、膝がガクガクと震えて立っていられなくなり、ビンセントに自らしがみついてしまうのであった。
「このまま抱いてしまいたい・・・・・・」
求められている嬉しさにコクンと頷いてしまいそうになったけれど、それでは待ち合わせの時間に遅れてしまいそうなので、僕は(駄目だよ)と首を横に振った。ビンセントもそれが分っているからあえて無理強いはしなかったけれど、そのまま二人でシャワーを浴びながら、ついついじゃれあってしまった。
お互いの身体にボディーソープを塗りあう。彼の手が身体中を這いまわり、そのくすぐったさに身を捩ってクスクス笑いながら、僕も彼の逞しい身体に手を這わせた。
そして、下半身のお互いのものをより丁寧に洗い上げてるうちに、昨日あんなにしたというのに、僕はその心地よさにあっという間にはじけてしまい、おもわずグッと彼のものを強く握ってしまったのが幸いして、ビンセントも達した。
そして、二人で抱き合いながら冷たいに水に身体を晒して、まだまだ熱くなりそうな昂ぶりを冷ましたのであった。
その時、僕はある事を思い出してしまった。昨夜、着ていた一張羅のスーツは、砂浜で及んだ行為のために、すっかり汚れてしまっていたのだ。
「あっ、どうしよう。昨日、ビンセントが砂浜であんな事したから、折角のスーツが台無しだよ。どうしよう。着ていく服がないよ」
慌てる僕に、ビンセントは『なんだそんなことですか』というような涼しい顔をして、言うのであった。
「それならホテルで用意しましょうか」
(レンタルがあるのかな)
と、僕はホッと安心して、約束の時間に遅れないようにと早めに僕達はコテージを出た。
そして、連れていかれたお店で、ビンセントは僕の為にレンタルじゃなくて、服だけでなくて靴までの一式を買ってくれた。
ネクタイ一つにしても、「えっ」と躊躇うような金額だったので、僕は「いいから」と一応言ってみたけれど、聞き入れてもらえるはずもなく、似合うからと言って、次々に決めていくビンセントに、僕は『お金持ちって』と、内心溜息をついてしまった。
「もう無駄使いして」
「貴方の為に使うのですから、決して無駄ではありませんよ」
自分が選んだ服を着た僕を、ビンセントは満足げに見つめながらそう言った。
「服を贈る意味には、着て欲しいと思うのと反対にそれを脱がしたいという欲望が隠されているのですよ」
恥ずかしくなるような事を平然として言うビンセントに、何を言っても敵わないと、つくづく思うのであった。
待ち合わせのカジノに着くと、もう皆は揃っていた。
「今晩は」
「秋生、素敵なスーツね」
「とてもよく似合うわ」
アンとキャシーが誉めてくれたので、僕は満更でもなく、ビンセントが見立ててくれたのだと、説明した。
「秋生ったら愛されてるわね」
「本当、羨ましいくらい」
確かにビンセントみたいな人に愛されるなんて、僕は幸せ者だなあとしみじみ思っていたら、「少しは否定くらいしたらどう」と反対に、怒られてしまった。
カジノは相変わらずの賑わいを見せており、僕は軽くルーレットで3回ほど勝負をして勝つと、あまり目立つのも嫌なので後は見るほうに回った。
「あっ、リサだわ」
アンが声を上げて示した場所には、ブラウンの長い髪を後ろで結い上げた美しい女性が、親子ほども歳が違うだろう男と一緒にいた。
キースは、二人を見ないようにして、別の場所へとさっさと移動してしまう。他の皆もキースと一緒に行ってしまう。でも、みんなの表情が青ざめていたのを、僕は見逃さなかった。
「どうしてキースより、あんな年上の人を選んだりするんだろう」
僕は分からなくて、そっとビンセントに尋ねてみた。
「恋愛に歳など関係ありません。私と貴方のように性別さえも超えて愛しあえる相手に出会えるなら、それはそれで幸せであり、他人がどうこう言えるものではありませんよ」
軽く窘められて、「そうだけどさあ」と僕は少し拗ねてみた。
「でも、彼女は仕事がしたいからって、キースと別れたんだよ。だったら、あんな人と付き合うなんておかしいと思うし・・・・・・」
そう言ったら、ビンセントは鼻でクスッと笑った。
「相手は彼女が勤める会社の社長でしょう。彼女は自分の野心のために彼を選んだのですから、満更、間違いというわけではありませんね」
「それは余計に悪いよ」
もしそうだとしたら、今でも彼女の事を好きなキースが可哀相だと思って、彼女に対して僕は怒りを覚えてしまった。
「出世のために恋人を裏切るなんて、そんなこと許せないよ」
「でも、世の中にはそう言う人間は多いのですよ。富や名誉のためなら、打算で割り切れるのです」
「僕はビンセントが、お金持ちだから好きなわけじゃないからね」
冷めたビンセントの言葉が哀しくて、僕は恨めしげに言ってみせた。
「分っていますよ。そういう貴方だから愛しているのですから」
周りに気づかれないように、ビンセントは僕の手をしっかりと握り締めてくれた。その手の暖かさは本物である。
「ごめんなさい。ただ、あんまり哀しいからさ。つい許せなくて」
「本当に割り切れるのなら、別にこんな形でキースの前に現れる必要はないでしょうにね。中途半端な思いは、人を傷つけるばかりです」
そう言うビンセントには、僕が理解出来ない何が分かるのかと、猛然と知りたくなってしまった。
「えっ、それってどういう事なの。教えてよ」
「元からこの旅行のことは、彼女は知っていたのでしょう?だとしたら、なんでわざわざ同じ時期にこの場所へやってきたのでしょうか?」
まるでミステリーの謎解きみたいに、僕はワクワクしながら、必死に考えた。
「偶然とは言えないよね。嫌だったら場所を変えればいいんだもの」
「わざわざ見せつける必要などないのですから、彼女がどういうつもりでキースの前に姿を現したかは、私には理解不可能ですね」
「それってキースにわざわざ見せつけに来たのには、理由があるってこと?」
「さあ、愚かな人の考えなど、私には分かりません」
ビンセントは意地悪く言ったけれど、それは僕にある考えを浮かばせた。
(もしかして、それって彼女はキースの事をまだ凄く意識しているっていうか、好きって事かな?)
ふと、彼女の方を見ると、彼女は年上の彼の側にいて一見、楽しそうに笑ってはいたけれども、その視線が人ごみの方を、さりげなく見つめている事に気づいてしまった。そして、その視線の先にいたのは、キースに間近いなかった。
(嘘。彼女ってキースの事、愛してる?)
打算で割り切り、恋人よりも仕事と名誉を選んだはずの彼女は、でも、本当は割り切れてなくて、キースに未練たっぷりだとしたら・・・・・・。
(分からないよ)
それならどうして、もっと自分の心に素直に従わないのだろうか。
(もしかしたら、彼女はちょっとでもキースの事を裏切ってしまった自分が許せないのかも。否、自分の選択を間違っているとは思いたくないのかもしれないし)
とにかく何か理由があるのでとしたら、このままではいけないような気がして、なんとしても彼女の気持ちが知りたくなってしまった。
「ちょっと聞いてくる」
僕はビンセントから素早く離れると、リサの方へ歩み寄って行った。ビンセントは少し呆れたような顔をしていたけれど、あえて止めるまではしなかった。
「あの、リサさんですか?」
僕は勇気を振り絞って、彼女に声をかけた。間近に見ても綺麗な女性だった。とても自分の野心のために、恋人を裏切るような人には思えない。
「はい、そうですけれど。貴方は?」
訝しげに問われて、僕は咄嗟に嘘をついた。
「僕は工藤 秋生って言います。僕、今、キースと付き合っています。貴方が彼の元カノって聞いて、是非、ご挨拶しとこうかなと思いまして」
ちょっと芝居がかった意味ありげな言い方をしてみた。
「えっ!?」
とたんに彼女の表情が強張った。
(やっぱり)
という確信を僕は感じた。
「少し、お時間いただけますか?」
僕を見る彼女の表情には困惑が浮かんでいたが、やがてコクリと頷いた。
「ええ、いいわ」
彼女は連れの男性に「知り合いだから」と言い訳して、僕と一緒にカジノの隅にあるカウンターバーへと、移動した。
席に座って飲み物を注文すると、彼女はすぐに質問してきた。
「貴方、キースとつきあっているって、本当なの?」
疑わしそうな問いかけに、僕はそうだと大きく頷いてみせた。
「はい。彼ってとっても優しくて、素敵ですよね。僕は貴方に感謝しないといけないのかな。貴方が彼を振ってくれたから、僕は彼と出会う事が出来たから」
「そうね・・・・・・・。だからなのかしら、私と会っても平気そうな顔してたから」
なんだか無神経な物言いに、僕はムッとしてしまった。
「別に分かれた相手に会ったからって、動揺しなくちゃいけないって事もないと思いますけれど。それに彼ったら僕に夢中だし」
ちょっと大げさだとは思ったけれど、挑発してみた。
「それはそうだけれど、ごめんなさい。キースが、男の子とつきあうなんて、ちょっと信じられないから」
「貴方だってあんなに歳の違う相手に乗り換えたんでしょう?仕事がしたいからって、随分な裏切りですよね」
正面からぶつかってみた。怒らせるつもりで言ったのに、けれども彼女は傷ついたような表情をした。
「そうね。彼ったら優しいから私の言うとおりに別れてくれたわ。理解がありすぎるのよね」
(えっ、それって勝手な言い分じゃない)
止めなかったキースを責めるような言葉に、僕はカッと頭にきたけれど、彼女の哀しそうな顔を見て、やっぱり彼女がここへ来たのは、キースをまだ愛していて、彼に自分を引き止めてもらいたいと願っているのではないかと思った。
「思いは言葉にしなきゃ通じないよ。貴方はすでにキースを傷つけてるんだから、今更未練があるからって、彼の前にノコノコ出てきてもらいたくないよ」
あてつけるように言うと、彼女はキッと僕を睨みつけてきた。
「そんなつもりはないわ」
「嘘だ!!だったらわざわざなんでここへ来たりしたの?キースの優しさは本物だよ。貴方の事を考えて、自分の気持ちを抑えて、別れたんだよ。それなのにその優しさを悪く言うのは、おかしいよ。引き止めて欲しいのなら、ハッキリとした態度をとるべきだと思う」
「貴方に何が分かるというの」
図星をつかれた彼女は酷く動揺してしまい、僕に怒りをぶつけてくる。
「女が仕事をしたいと思っても、なかなかそのチャンスを手に入れる事は、難しいのよ」
「それは男だって同じだよ。自分の才能だけでなく身体を使う事も、確かにありだとは思うけれど、それならそれで自分で選んだ道なんだから、後悔なんかしないでよ。引き止めてくれたらなんて、都合のいいこと考えないでよね」
自分でも随分と冷たい事を言っているのは、分かるけれど、優柔不断な態度でこれ以上キースを傷つけるのは止めて欲しいと思った。
(そんなに好きなら、素直になればいいんだ)
仕事ってなんだろうって思う。やりがいのある仕事、自分にむいている仕事なんて、そんなにピッタリ当てはまるものに出会えるなんて事、なかなかないのかも知れない。好きな事を仕事に出来たら、それは本当に幸せだと思うけれど、きっとそういう恵まれた人って一握りの人だと思う。
後は、生活のため、自分のしたい事のためとどこかで割り切って、それでも一生懸命に毎日働いている人が多くて、そういう人達の努力の積み重ねが、世界を支えているのだ。
「キースには僕や皆がついているから、貴方は安心して好きな道を行って下さい。話はそれだけ。お幸せにね」
僕はそれだけ言うと、彼女の飲み物の分もお金を払って、その場を去った。後は彼女がどうしたいと望むかである。
ハッキリいって彼女は好きになれないけれど、キースには幸せになってもらいたい。
(うまくいってくれるといいけれど)
僕はそう願いながら、ビンセントの元へと戻った。
「どうでしたか?」
「焚きつけてきたから、後は結果待ちかな」
するとビンセントは可笑しそうに言った。
「貴方も随分と大人になりましたね」
「誰かさんに鍛えられたから。僕だっていろいろと悩んだり不安になったりしたんだよ」
「それは、私も同じですよ。貴方のせいでハラハラし過ぎて寿命が随分と短くなった気がしますよ」
不死身の青龍の寿命ってどのくらいと突っ込みたくなったけれど、また言い負かせられそうなので、僕は黙ってリサの様子を見守っていた。
彼女はしばらくカウンターに座っていたけれど、スッと立ち上がると、年上の男性の所ではなくて、キースの元へとまっすぐに歩いていった。
戸惑っているようなキースの表情だったけれど、やがて二人は、一緒にカジノから出て行った。
「上手いくかどうか賭けますか?」
ビンセントに尋ねられて、僕は即答した。
「上手くいくに賭ける」
「私も上手くいくです」
二人ほとんど同時に答えていたので、僕達は思わず顔を見合わせて笑ってしまった。
「賭けにならないよね」
「そうですね」
彼に手を取られて、引き寄せられてしまう。
「さあ、私達も帰って、愛を確めあいましょうか?」
冗談っぽく囁くビンセントが、本当はかなり本気なのを僕は感じてしまった。だって、僕もそう思ってしまったから。
「そうだね」
僕達は共犯者のようにまた笑いあって、皆の所へ言った。
「秋生、一体リサと何をはなしていたの?」
「リサったら、何か真剣な顔をして、キースに話があるからって言ったわ」
僕はちょっと嘘をついて彼女を挑発したことを、簡単に皆に説明した。
「僕としては、きっと二人は上手くいくんじゃないかと思うんだけれど」
「そうなったらいいけど・・・・・・。まあ、後はキースとリサのお互いの気持ちよね」
皆も納得してくれたみたいだったので、僕達は少し疲れたから今日はもう帰ると言い訳して、カジノを後にしたのであった。
ホテルとかコテージまでの道を、僕達は手を繋いでゆっくりと歩いた。思えばこんな事、始めてかもしれない。いつも二人ではいたけれど、こんな事が出来るのはリゾート地だからこそじゃないだろうか。誰も僕達の事を知るわけないし、男同士のカップルであることを隠す必要もない。本当はちょっとはまずいかもしれないけれど、香港にいる時には、絶対に出来ないことだった。でも、ここにはそれを許してくれる開放された雰囲気があった。
「ここに来て、良かった」
僕がポツリというと、ビンセントも「そうですね」と頷いた。
「貴方とこうして手を繋いで一緒に歩けるなんて、感激ですよ」
どんな状態になろうとも、今までも、そして、これからもお互いを愛する気持ちは変わらないだろう。こうしてお互いの手の温もりを確認しあうだけで、言葉や激しいキスやHじゃなくても、幸せを感じる事が出来るのだ。
「ずっとこうして過ごしたい気もするけれど、遊んでばかりだときっとすぐに退屈しちゃうんだろうな」
「貴方となら、私は退屈なんてしないと思いますけれど」
意地悪くフッと笑うビンセントに、「このおっ」と拳を作って、ブンと宙を殴る振りをしてみせると、ビンセントはその手をパッとつかんで、手の甲にキスをした。
「貴方のいる場所が、私にとっての楽園です」
「!!」
どうしてそういう事をサラリと口にしてくれるのかと、思いながらも、僕は嬉しくて、彼の腕に縋りついた。
「もう、そういう恥ずかしい事、言わないでよね」
僕は、夜空に輝く満天の星を見上げながら、自分が宇宙一の幸せ者だと確信する。
(僕にとってもビンセントがいる場所が楽園だよ)
そう心の中で告げてみるのであった。
「秋生、元気でね」
「きっとまた会いましょう」
「楽しかったよ、またな」
「元気でな」
テリーにアン、エドにキャシーが代わる代わるに僕を抱き締めてくれた。
「皆も元気でね。絶対、また会おうね」
折角仲良くなれたのにこれでお別れなんて嫌である。
「秋生、ありがとう。貴方に出会えて本当に良かった」
「キース、僕もだよ」
彼がいてくれたお陰で、最低で始まった旅行は、最高の想い出になったのだから。
僕は、キースに寄り添うようにたっているリサに、微笑んだ。
「お幸せにね」
「ありがとう」
はにかむように笑うリサ。キースと話し合って、自分の気持ちを正直に伝え結果、予想通り、二人は元の鞘に収まったのであった。
「良かったね、キース」
「ありがとう」
僕は皆に手を振って、プライベート・ジェットの中へと乗り込んだ。ビンセントはすでに座席に座っている。
これで楽しい旅は終わってしまうのかと思うと、少し残念だったけれど、あの雑多な香港がなんだか懐かしくて早く帰りたい気持ちも強くなっていた。
僕達は座席について、窓から見送ってくれる皆に手を振った。
やがて、動きだすジェット。いろいろな想い出からの離脱って感じがして、少し寂しくもあったけれど、側にいるビンセントと共にあることが、自分にとって何より幸せなのだという事が分かっていたので、心は軽かった。
「お土産もいっぱい買ったし、皆に早く会いたいな」
香港で待っていてくれる人達の顔が、懐かしく思い出されて、心がソワソワ落ち着かない。
「あのね、次はオーストラリアへ行こうよ。キースが招待してくれるって。牧場で馬に乗せてくれるってさあ。楽しみだよね。絶対に行こうね」
「はい」
頷きながらも、ビンセントは心の中で、帰ったら早速に牧場を買おうと決めるのであった。
(馬ならいつでも私が乗せてあげますから)
他の男との約束を楽しみにしている姿は、決して快いものではない。
秋生の喜ぶ顔を見るためならば、牧場の一つなど安い買い物だと思うのであった。
おわり